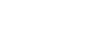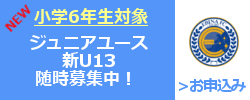3/14(土)くもり
第29回座間市少年サッカー招待杯が相模川河川敷グランドにて行われました。
初戦の相手は、 FC相模野さん。
ここ最近、県選手権や市内大会などは11人制。
今回は8人制という事で、レギュレーションがコロコロ変わるので子どもたちも大変ですね。
試合は、開始早々に先制!
ナルミのここ最近の得点力は凄いですね。
ま、色々ありましたから・・・。
頑張って貰いたいですね。
主力となる選手たちの選択しているプレーとコーチが考えているプレーにそれ程違和感はないので、こちらからはアドバイス程度。
原理原則を良く理解してくれているので、自分で判断を変える事が出来ますからね。
セオリーとアドリブを上手く使い分けてくれています。
そうなると、課題となってくるのが控え組の5年生と4年生を中心とするパックアップメンバー。
今、何をすべきか?
と、いう場面では自分で判断が下せないんですね。
ここが主力と言われる選手との差かな。
何を観て、何を考え、何をするべきか?
サッカーは、基本的に自由にしかならないし、流動的な場面が多いですよね。
だからこそ、常にトレーニングで『何を観て、何を考えるべきか?』を言い続けているのですけどね。
逆にこれが悪いのかな?
言い続けるから覚えなくても良いと思っているのかな?
ってことは、海老名FCを卒業してコーチたちがいなくなったら君たちはどうするのかな・・・?
自分はジュニアユース(中学生)年代もユース(高校)年代も指導して来たので、今が大事だって事がホントに良くわかります。
中学生になっても高校生になっても成長は出来るのですが、この小学生年代が一番頭もやわらかくて色々と考える事が出来る。
だからこそ、『何を観て、何を考え、何をするべきか?』をオートマチックに出来るように習慣化させることが大事だと思うんですね。
もちろん、それを表現するテクニックは必要になってくる。
でも、テクニックがあっても考えが無ければ、または遅ければチャンスは潰れてしまいます。
だからこそ、素晴らしいアイデアを考える能力とそれを表現するテクニックの両方が大切になるんですね。
原理原則を知れば、アドリブも効きます。
これが駆け引き。
こんなことを楽しく学ぶ事が出来る年代なんですね。
8年位前、海老名市の有馬中学校でサッカー部の指導をしていた頃、卒業して行く3年生の子に言われたことが今でも頭に残っています。
『もっと早くイイジに逢いたかった。そうすれば、もっとサッカーを楽しめたと思うし、もっと学びたかった。でも、3年間充実していたし、楽しかった。ありがとうございました。』って。
ホントに嬉しい言葉でしたね。。。
だからこそ、今の彼らに妥協せず指導して行きます。
ちゃんとコーチについてきてよ〜(^_^)
必ず、目的地まで連れて行くからね。
さて、話は脱線しましたが、初戦は9−1で見事勝利。
幸先の良いスタートをを切ることが出来ました。
第2戦挑みます(^o^)/